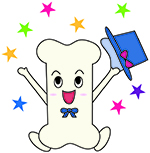【厚生労働省】柔道整復療養費検討専門委員会 議論まとめ
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

厚生労働省で行われる、柔道整復療養費検討専門委員会の議論をまとめています。
この会議で議論されたことが料金改定に反映されます。
第26回(2023年10月26日開催)
主な議題……
・柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について
柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について
今回の検討専門委員会は、前回に引き続きマイナ保険証でのオンライン資格確認の導入について議論されました。
この記事は組合員限定コンテンツです。
ログイン後に続きが表示されます。組合員限定コンテンツについて
ログインできない場合は、ご覧いただいているアプリを一度閉じてから、GoogleChromeやsafariでアクセスのうえ再度お試しください。